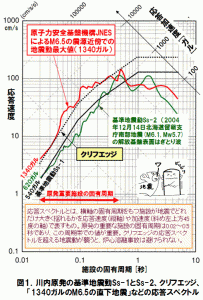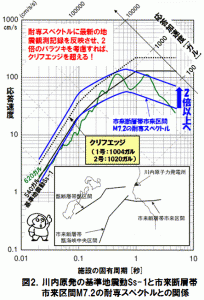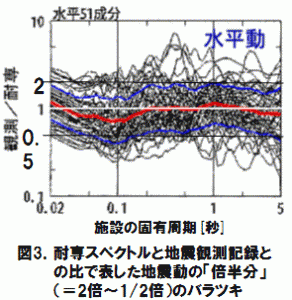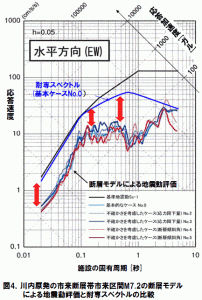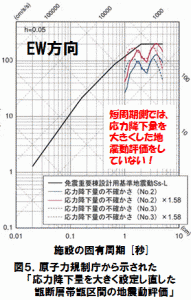1月16日交渉で、原子力規制委員会の論理が遂に破綻!
1340ガルの地震動を全原発に取り入れよ!
姶良カルデラ噴火への規制委対応策を示せ!
呼びかけ: 川内原発建設反対連絡協議会、川内つゆくさ会、反原発・かごしまネット、まちづくり県民会議、川内原発活断層研究会、東電福島原発事故から3年-語る会、さよなら原発:アクションいぶすき、原発ゼロをめざす鹿児島県民の会、かごしま反原発連合有志、原子力発電に反対する福井県民会議、サヨナラ原発福井ネットワーク、原子力資料情報室、若狭連帯行動ネットワーク(事務局担当)
連絡先:〒583-0007 藤井寺市林5-8-20-401 久保方 TEL 072-939-5660 dpnmz005@kawachi.zaq.ne.jp
または 〒591-8005 堺市北区新堀町2丁126-6-105 若狭ネット資料室(長沢啓行室長)
TEL 072-269-4561 ngsw@oboe.ocn.ne.jp http://wakasa-net.sakura.ne.jp/www/
原子力規制委員会への申し入れ
原子力規制委員会・規制庁との交渉記録(2015.1.16)
交渉のまとめ
2015年1月16日の原子力規制委員会との交渉では下記の通り、大きな成果を得ました。公開質問状への賛同団体・個人は100団体504個人に拡大しました。カンパも約18万円が集まりました。厚く感謝申し上げ、これからもご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。
<2015.1.16原子力規制委員会との交渉のまとめ>
地震と火山の問題で、原子力規制委員会・規制庁の論理は遂に破綻しました。2015年1月16日の私たちとの交渉で、原子力規制委員会・規制庁は、次のように重大な事実を認めました。
地震については次の通りです。
(1)原子力安全基盤機構JNESによる「M6.0の縦ずれ断層による地震動評価結果の最大値」と北海道留萌支庁南部地震の観測記録とは大体合っており、地元説明会やパブコメでの回答で「(JNESのモデルでは)厳しい条件を設定」していると指摘したのは「書きすぎている可能性がある」。
(2)1340ガルの地震動評価は「超過確率を算出するために行った仮想的なモデルによる試算だから適用しない。」といいながら、「実際の発電所の評価などに適用すべきかどうか、地震のモデルとしての再現性という点で妥当かどうかを専門家も含めて改めて検討する必要がある。」
(3)「(JNESの)計算のモデル自体ではなくて、ここで出てきた超過確率自体が妥当かどうか、実際に現実とどのぐらい合っているかは正直に言って良くわからない。そういうこともあるので、確率論的な評価は日本では適用ができていない。」
(4)「地震動評価全体としての学術的な知見の蓄積とそれ自体の見直しみたいなやつというのはトータルでやっぱりどこかでやる必要はある。」
要するに、JNESによる地震動評価結果が留萌地震の観測記録と良く合っていることから、JNESのモデルが「仮想的」=非現実的だと決めつけるだけでは「1340ガルの地震動」を排斥しきれず、その基準地震動への適用可能性について改めて検討すべきであることを認めたのです。
火山については次の通りです。
(1)九州電力の示した「姶良カルデラに関する監視体制の移行判断基準(案)」において、地殻変動が通常の5~10倍になった時点でカルデラの活動だと判断されれば「対処準備・燃料体等の搬出等」で対応することになっているが、その時点で「60年以上の余裕がある」との九州電力の主張については、規制委員会として「評価していない。」「60年以上余裕があるかどうかはわからない。」
(2)九州電力の判断基準とは別に、「もっと早い段階で、マグマ供給率が変化してきた段階で、止めたり、燃料体を搬出していく」必要があり、「原子力規制委員会としても、ある程度の変化が観測された場合には運転停止命令を出したり、規制側からのアクションが必要だ。」「まず、事業者が対応するが、規制委員会としても必要な命令は出していく。」運転停止命令を出す時点で「5年の余裕があるかという具体的な数字での判断はしていない。」
(3)「マグマ供給率の変化がいくつになったら運転停止命令を出すとか、具体的な数字を規則として決めてしまうと、もっと早い段階から止めるべきものを見逃したりしてしまう可能性もあるので、そのときの状況に応じて判断していく必要がある。」
(4)「原子力規制委員会からどういうアクションを起こすかということについては、火山モニタリングチームで検討していく。」
結局、「姶良カルデラ噴火の可能性は十分小さい」と決めつけながら、運用期間中の噴火の可能性を否定できないのでモニタリングを行うけれども、九州電力の判断基準(=地殻変動が5~10倍になった時点で噴火まで60年以上の余裕がある)は甘すぎること、規制委員会として九州電力より早い段階で予兆かどうかを判断して運転停止命令を出すこと、しかし、その判断基準は現存せず、これから検討していくこと、しかも、運転停止命令を出す時点で5年の余裕があるかどうかは分からないことが明らかになったのです。
地震と火山に関する以上の内容は、昨年の川内原発の審査書には一切書かれておらず、鹿児島県内の地元説明会でも全く説明されていません。今回の交渉で初めて明らかにされた内容です。高浜3・4号の審査書案でも全く触れられていません。
「震源を特定せず策定する地震動」で検討対象にしている16の地震観測記録はここ十数年のものにすぎず、決定的に不足しており、それを補うためにはJNESの地震動評価結果を検討対象に入れるべきです。そもそも「震源を特定せず策定する地震動」では所在不明の伏在断層を対象にしており、震源断層を原発ごとに設定できないため「仮想モデル」になるのは当たり前です。「仮想モデル」だからという理由でJNESの地震動評価結果を無視するのは原子力規制委員会の良識を疑います。「M6.5の横ずれ断層による1340ガルの地震動」を全原発の基準地震動として採用すべきです。
姶良カルデラ噴火についても、原子力規制委員会は、九州電力による火山モニタリング態勢=「地殻変動が5~10倍になった時点で対応」では遅すぎる、その時点で「噴火まで60年以上の余裕があるかどうかはわからない」としながら、その訂正を求めず、基本設計をそのまま了承していたのです。保安規定の中にもそのまま書き込むことを黙認し、これとは別に原子力規制委員会としてもう少し早い段階で運転停止命令などを検討していくというのです。しかも、その判断基準は存在せず、あらかじめ決めることもしない。運転停止命令を出してから燃料搬出までに必要な5年以上の余裕が噴火までにあるかどうかも分からないというのです。「噴火対応の第一義的責任は九州電力にある」というのであれば、甘すぎると判断した「九州電力の噴火対応方針」の訂正を求めるべきです。そうしないのは、原子力規制委員会にも噴火対応の方針がなく、「できない」からです。この方針を作るには時間がかかりすぎ、いつまで経っても再稼働できないからです。とりあえず、川内原発を再稼働可能な状態にして、その安全は保証せず、地元には詳しく知らせず、再稼働が承認されるかどうかの判断には関与せず、噴火対応を別途検討していくというのが原子力規制委員会の今、現に取っている対応なのです。こんなことは許せません。
原子力規制委員会が地震と火山で今取っている対応は、福島第一3号炉のプルサーマル計画を推進するため貞観津波の評価を棚上げにした原子力安全・保安院時代の対応と全く同じです。フクシマを教訓とし、地に落ちた国民の信頼を回復したいのなら、地震と火山の審査をやり直すべきです。
以下では、もう少し詳しく報告します。
(続きはこちらをご覧ください)