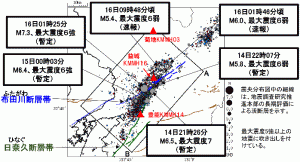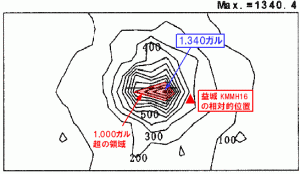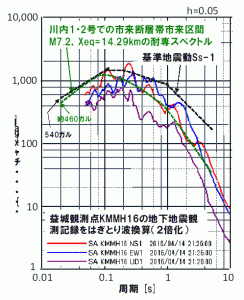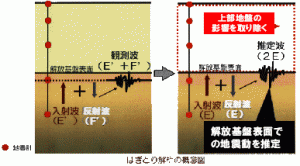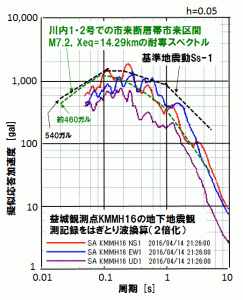若狭ネットニュース第164号を発行しました。
いよいよ、最終決戦です!「原発コストの託送料金への転嫁」反対署名を1月29日の討論集会(大阪)で集約し、2月初めに提出しますので、最後の踏ん張りをお願いします!
第164号(2016/12/21)(一括ダウンロード2.0Mb)
巻頭言-福島事故関連費と原発コストを「電気の託送料金」に転嫁しないで!署名運動にご協力を!
(1)ママとわかさちゃんの井戸端談義
今知らないと、将来に禍根を残す「託送料金による東電救済」の秘密
(2)地震調査研究推進本部が2016年12月9日に断層モデルのレシピを再改定
レシピ改定の意義と大飯・高浜原発基準地震動への影響
大阪府立大学名誉教授長沢啓行
署名:福島事故関連費と原発コストを『電気の 託送料金』に転嫁しないでください
(署名用紙・ダウンロード、署名用紙Word版はこちら、リーフレット・ダウンロード)
署名集約先:〒583-0007 藤井寺市林5-8-20-401 久保方
TEL 072-939-5660 e-mail dpnmz005@kawachi.zaq.ne.jp
呼びかけ団体:若狭連帯行動ネットワーク(事務局)、双葉地方原発反対同盟、原発の危険性を考える宝塚の会、日本消費者連盟関西グループ、関西よつ葉連絡会、安全な食べものネットワークオルター、サヨナラ原発福井ネットワーク、福井から原発を止める裁判の会、吹夢キャンプ実行委員会、福島の子供たちを守ろう関西、さよなら原発神戸アクション、さよならウラン連絡会、おかとん原発いらん宣言2011、原発ゼロ上牧行動、STOP原子力★関電包囲行動、とめよう原発!!関西ネットワーク、さよなら原発なら県ネット、地球救出アクション97、ヒバク反対キャンペーン、さよなら原発箕面市民の会、チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西、環境フォーラム市民の会(豊中)、科学技術問題研究会、さかいユニオン、大阪自主労働組合、社民党福島県連合、フクシマ原発労働者相談センター、日本消費者連盟、原子力資料情報室
<巻頭言>
私たちは、多くの市民団体と力を合わせて、11月8日から街頭や職場で「電気の託送料金への転嫁」反対署名に取り組んでいます。11月19日(土)、26日(土)はJR京橋駅前で署名活動、11月27日(日)「川内原発は二度と動かさない御堂筋デモ」や12月3日(土)「もんじゅを廃炉へ全国集会」(敦賀市)に参加して署名をアピール、12月4日(日)原発ゼロ上牧行動のお世話でJR高槻前で署名活動、12月10日(土)「沖縄に基地は入らないおおさか総がかり集会in扇町公園」で署名活動、12月11日(日)チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西結成25周年集会で署名アピール、12月17日(土)阪神「尼崎駅」周辺で署名活動、12月23日(金:祝)にも11時からJR京橋駅前で年内最後の署名を予定しています。毎回、十数名で署名を行い、まずまずの反応です。「東電や電力会社が責任を持って負担すべきなのに、私たち消費者が負担させられるのはおかしい!」という怒りの声が続々と聴かれます。
全国各地からも署名が届いてきて、徐々に積み上がってきていますが、まだ数万のレベルには届いていません。来年1月末の第一次締切に向けてもう一踏ん張りしたいところです。
この問題が、もっとみんなに明らかになれば、反対署名は広がると確信しています。年末、年始にお会いする人たちにもこの問題を話していただき署名を拡げてください。
がんばりましょう。
託送料金の転嫁は8.3兆円から8.6兆円に
経済産業省は10月内部資料の段階で8.3兆円を託送料金へ転嫁しようと狙っていました。
その一部は断念されましたが、新たに付け加わったり、試算値が増えたりした結果、現時点で8.6兆円が託送料金へ転嫁されようとしています。
当初は、福島事故損害賠償費一般負担金3兆円、福島原発廃炉費4兆円、原発廃炉費積立不足金1.3兆円の計8.3兆円でした。
しかし、福島事故損害賠償費は3兆円の一般負担金の託送料金への転嫁を断念する代わりに一般負担金の「過去分」と称して2.4兆円を新たに託送料金へ転嫁して新電力にも負担させ、福島原発廃炉費は4兆円から6兆円に増え、原発廃炉費積立不足金は震災後廃炉になった原発の分0.05兆円に限定される一方、廃炉時未償却資産0.15兆円が新たに付け加えられ、結果として計8.6兆円に増えました。
今回断念された損害賠償費一般負担金3.3兆円や原発廃炉費積立不足金1.2兆円、未償却原発資産2.5兆円の計7.0兆円は「託送料金への転嫁」予備軍として残されており、今後、機を見て追加される可能性があります。
特に、未償却原発資産は再稼働のための対策工事費が最大3.3兆円も計画されていて、これらが未償却原発資産に追加されれば未償却原発資産は5.8兆円にも増え、計10.3兆円が予備軍として残ることになります。
また、福島原発廃炉費追加分6兆円は溶融燃料デブリを取り出して輸送する費用の見積もりですが、取り出せる技術的根拠もなく致死的高線量下の作業ですのでロボット開発費がかさみ、取り出したあと何十年、何百年と管理し続ける費用を考えると天井が見えないのが実態です。
2016年12月20日原子力災害対策本部決定
損害賠償費 5.4兆円→ 7.9兆円(+ 2.5兆円)
廃炉対策費 2 兆円→ 8 兆円(+ 6 兆円)
除染費 2.5兆円→ 4 兆円(+ 1.5兆円)
中間貯蔵施設費 1.1兆円→ 1.6兆円(+ 0.5兆円)
合計 11 兆円→21.5兆円(+10.5兆円)
※交付国債による原賠機構から東京電力への資金援助額は廃炉対策費を除く13.5兆円(現在は9兆円)
東電を破産処理し、債権放棄で資金捻出を!
経済産業省や政府は、「東電をつぶせば損害賠償も廃炉も進まない。」「廃炉が進まないと復興が進まない。」だから、「東電をつぶさず、経営が安定するよう支える」と説明しています。東電も、福島第一原発の廃炉現場へ高校生を見学させた際、「もし、東電が破産したら廃炉事業はどうなるんですか?」と質問する高校生に、「廃炉が進まないと、復興は進まない。東電を潰せばいいと言う人がいるが、東電がやらなくてはほかの誰が(廃炉を)やるのか。そのために3万3千人の社員ががんばっている」(日本経済新聞11月28日)と、得々と答えています。それは間違っています。
そうではありません!
東電を破産処理すれば、私たち電力消費者と国民の負担はずっと軽くなります。
福島事故を起こしたのは東京電力です。東京電力に事故の責任があります。
福島原発でボロ儲けをしてきた東電役員、株主、金融機関は、事故の責任を取らされないまま、すでに5年9か月が過ぎてしまいました。損害賠償費や汚染水対策・廃炉費が膨れあがった今こそ、その責任をキチンと問うべきです。
株主や金融機関のもつ負債、2.9兆円の社債、1.9兆円の長期借入金、流動負債2.8兆円を債権放棄させ、純資産2.2兆円を合わせれば9.8兆円もの資金を生み出せます。これを損害賠償費や廃炉費に投じ、それでも足りない分は、累進課税の税金や大企業の法人税で補填すべきではないでしょうか。
もちろん、その前提として、重大事故の可能性を前提とした原発再稼働を止め、再処理・プルトニウム利用政策を断念すべきです。
損害賠償費一般負担金「過去分」2.4兆円の怪
損害賠償費一般負担金は原子力事業者による相互扶助制度でお金を出し合う形になっているにもかかわらず、自分の利益からは1円も出さず、すべて電気料金のコストに転嫁して回収しています。
にもかかわらず、電力小売の全面自由化が始まると、電気料金が下がって回収できなくなるのを恐れて、規制料金制度が残る「託送料金」にそのまま転嫁して新電力からも回収しようとしているのです。
経産省の説明では「原発重大事故による損害賠償費は原子力発電が始まった約50年前から用意しておくべきだったが、2011年より前には今の相互扶助制度はなかった。この分を『過去分』と呼び、これについては原発を持たない新電力も含めて幅広くすべての電力消費者に支払ってもらう。『過去』には原発による“安い電気”の恩恵を受けたんだから当然だ」と。
全くおかしな話です。もともと、経産省も大手電力も「原発は絶対に重大事故は起こしません」と宣伝し、さらに「原発の電気は安い」と、ウソを言い続けてきたではありませんか。その人たちが、福島事故の責任を棚上げにして、恥じ知らずにも、このような屁理屈をとくとくと述べ、「託送料金」を通して損害賠償費一般負担金の「過去分」の支払いを強要するのです。
絶対に許せません。
経産省がまず一番にやるべきことは、原発重大事故がもたらす甚大な被害を考えれば、「原発を重要なベースロード電源と位置付けたエネルギー基本計画」そのものを撤回することです。
「損害賠償費や福島廃炉費などを電気の託送料金に転嫁する仕組み」を作り上げることではなく、東電を破産処理し、株主や金融機関に債権放棄させて資金を生み出し、事故の責任を明らかにし、責任を取らせたうえで、できる限り国民負担を軽減しながら、国の責任で原子力被災者を全面的に救済し、福島原発廃炉に全力を注ぐことなのです。原発にしがみつき、原発の再稼働をもくろむことではありません。
廃炉費追加分6兆円を「託送料金」へ潜り込ませる
最も膨れ上がったのが、これまで2兆円と見積もられていた廃炉・汚染水対策費です。経産省は8兆円という数値を出していますが、これは、原賠機構(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)が有識者からヒアリングした結果に基づく数値であり、スリーマイル島原発事故の約1,000億円をベースとしてその60倍とみて推定した試算にすぎません。
福島の場合はスリーマイル島原発とは異なり、致死的な放射線量のため近づくことすらできず、デブリがどこにどのように存在しているのかさえ分からないのです。
30~40年で回収するとしていますが、実際のところ、技術的な見通しが全くたたないのです。8兆円という数値は天井知らずに上昇する可能性があるのです。
経産省は、この廃炉費を東京電力管内の「託送料金」を高いままに据え置き、得られた利益を消費者に還元せず、原賠機構に預けて「廃炉基金」にするという方法を編み出しました。この方法が導入されると、電力消費者の知らない間に「託送料金」から廃炉費が回収され、8兆円からさらに膨れあがってもドンドン回収されることになってしまいます。
東京電力管内だけでは資金不足ということになれば、全国の託送料金へ広げられていくことでしょう。それも経産省令を少し修正すれば済むようになってしまうのです。実に巧妙で、国民だましの恐るべき方法です。
今は、「託送料金」の利益が貯まりすぎたり、コスト削減率が5%を超えると託送料金を下げることになっていますので、これを高止まりにできるよう法令を改定しようとしているのです。本来下がるはずの託送料金が高止まりするのですから、電力消費者が知らぬ間に負担させられることになるのです。
世耕経産大臣は「原発は安い」というが、それなら・・・
経済産業省の東京電力改革・F1問題委員会は12月9日、福島原発事故関連費が21.5兆円になるとの試算を示し、その大半を託送料金に転嫁し、新電力を含めて回収する方向性を打ち出しましたが、その3日前に世耕経産大臣は「原発は安い」との発言をくりかえしました。しかし、「安い」のなら原発コストを託送料金に転嫁する必要などないはずです。
立命館大学の大島堅一教授によれば、有価証券報告書に記載された実際の原発コストと今回の21.5兆円の事故コストから計算し直した原発コストは13.1円/kWhになり、火力の9.9円より3円以上高くなったといいます。
つまり、国民にとって、原発は高くつくのです。それが、電力会社にとって安くなるのは、21.5兆円の事故コストを電力消費者や国民に転嫁できるからです。
電力会社の実際の負担にならない限り、原発のコストが高くても、電力会社にとってのコストにはならないのですから。
重大事故を起こした東電と原発を推進する電力会社を救済するため、経産省は「福島事故関連費や原発コストを託送料金へ転嫁する仕組み」作りに躍起となっています。
今、その動きを止めなければ大変なことになります。30年、40年と続く「最悪の国民への負担転嫁プログラム」が作られ、動き始めようとしているのですから。
この動きを押しとどめ、明るい社会を子や孫にバトンタッチするためにも「電気の託送料金に転嫁しないでください」の署名に全力を挙げましょう。
2017年1月末が署名の第一次締切です。2月初めに経産省へ提出し、追及します。
そのための署名集約討論会を1月29日に開きます。
ぜひご参加下さい。署名へのみなさんの一層のご支援をお願いします。